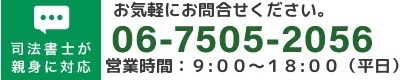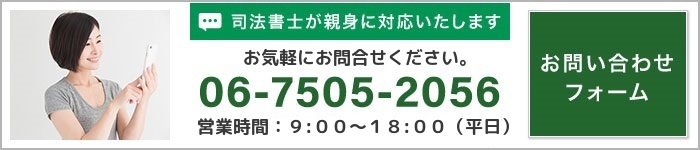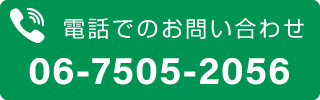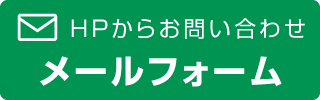近年の日本においては、1年間に約12万社の会社が設立され、約4万社以上が休廃業・解散をしていると言われています。
設立数が減り、休廃業・解散が増加する傾向にあるとはいえ、未だ多数の会社が毎年設立されています。
そこで今回は、会社設立の手続のポイントや流れとその機関設計について、解説します。
このページの目次
会社の成立の要件
会社法で定められる会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
この4種の会社が成立するための要件は、その本店の所在地において設立の登記をすること、と定められています。
つまり、会社は設立の登記をすることによって、初めて誕生するということになります。
株式会社の機関設計
会社を設立することで、起業したり法人なりしたりすることをご検討の場合、どの種類の会社にするのか、どのような機関設計にするかは、大変悩まれるのではないでしょうか。
近年は、合同会社の設立数が相当に増えているので、合同会社も候補に入ってくるのではないでしょうか。なお、株式会社と合同会社の設立の比較にについては、こちらです。
今回は、設立する会社は大会社ではない株式会社(資本金5億円未満又は負債の額が200億円未満)であるとした上で、株式会社ではどのような機関設計が可能なのか、解説していきます。
なお、公開会社とは、発行している株式の一部又は全部に譲渡制限の付いていない会社の事を指します。
必ず置かなければならない機関
・株主総会
・取締役
・代表取締役
置くことができる機関
・取締役会
・監査役
・監査役会
・会計監査人
・会計参与
・監査等委員会
・指名委員会等

機関設計のルール
・取締役会設置会社は監査役を置かなければならない。但し、非公開会社において、会計参与を置いた場合は、この限りでない。
・会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない。
・監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならず、会計監査人を置かなければならない。
・監査等委員会設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
(※大会社に関するルールは省略します。)
中小の非公開会社(株式の全部に譲渡制限がある)の場合の取り得る機関設計のパターン
1)取締役
2)取締役+会計参与
3)取締役+監査役
4)取締役+監査役+会計参与
5)取締役+監査役+会計監査人
6)取締役+監査役+会計監査人+会計参与
7)取締役会+会計参与
8)取締役会+監査役
9)取締役会+監査役+会計参与
10)取締役会+監査役+会計監査人
11)取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
12)取締役会+監査役会
13)取締役会+監査役会+会計参与
14)取締役会+監査役会+会計監査人
15)取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
16)取締役会+指名委員会等+会計監査人
17)取締役会+指名委員会等+会計監査人+会計参与
18)取締役会+監査等委員会+会計監査人
19)取締役会+監査等委員会+会計監査人+会計参与
中小の公開会社の場合の取り得る機関設計のパターン
1)取締役会+監査役
2)取締役会+監査役+会計参与
3)取締役会+監査役+会計監査人
4)取締役会+監査役+会計監査人+会計参与
5)取締役会+監査役会
6)取締役会+監査役会+会計参与
7)取締役会+監査役会+会計監査人
8)取締役会+監査役会+会計監査人+会計参与
9)取締役会+指名委員会等+会計監査人
10)取締役会+指名委員会等+会計監査人+会計参与
11)取締役会+監査等委員会+会計監査人
12)取締役会+監査等委員会+会計監査人+会計参与
以上が、大会社以外の会社で取り得る機関設計の全てのパターンですが、中小企業の場合は、そのほとんどの会社には会計監査人や指名委員会等、監査等委員会は設置されていませんので、これらの機関の設置を検討しなくても支障はないと思われます。

株式会社設立の流れ
株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立というのは、会社設立の発起人が会社の株式を全て引き受ける設立です。募集設立というのは、設立にあたり、発起人以外の第三者の出資を受けて株式を引き受けてもらう設立のことです。
以下に、発起設立の場合の会社設立の手続きの簡単な流れを記載します。
①必要事項の決定及び準備
商号や会社の目的、役員、資本金、株数について決めたり、会社実印を作ったりします。
![]()
②定款作成
会社の憲法である定款の原案を作成します。
![]()
③定款認証
公証役場にて定款を認証してもらいます。なお、当事務所にて電子定款で申請すると印紙代4万円が0円になります
![]()
④資本金の払込み
資本金となる金銭を払い込みます。現物出資も可能です。
![]()
⑤設立時調査
設立時取締役等による設立事項の調査を行います。
![]()
⑥登記書類作成
上記の決定や払込みに基づいて登記に必要な書類を作成します
![]()
⑦設立登記申請
法務局に登記申請をします。申請日=設立日となります。
以上、機関設計や会社設立の流れについて解説しました。なお、株式会社設立の登記申請手続きの解説については、こちらをご覧ください。
豊中司法書士ふじた事務所では機関設計に関するアドバイスはもちろんの事、会社設立登記申請手続きの代行もしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。