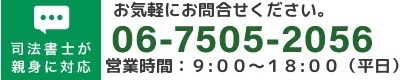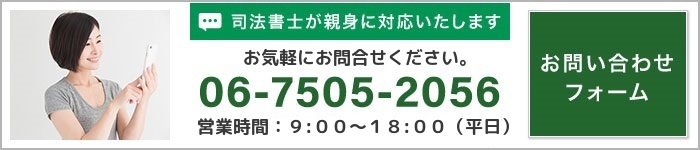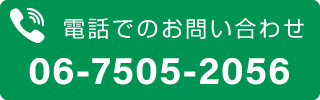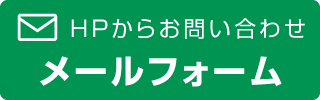相続が生じたのだけれども、どこに相談したら良いか分からないという方は多いのではないかと思います。
相続の相談は、専門家である司法書士にするのが、最も適切で、かつ、リーズナブルになります。
相続と言っても、その手続の種類は様々です。弊所の司法書士が、ご相談者様のお話をじっくりお聞きして、最適な手続きをご案内しますので、ご安心ください。
相続の約90%は、司法書士のみの関与で解決が可能です。残りの10%に該当する相続税の申告や遺産分割調停・審判については、弊所から税理士・弁護士をご紹介しますので、まずは、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。
以下に、各種の相続手続きについて、ご案内をいたします。
このページの目次
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)は、相続によって発生する全ての手続きを丸ごと司法書士に任せることができるものです。
具体的には、不動産の相続登記、戸籍調査、遺産分割協議書作成、相続放棄、預貯金の相続による解約、株式の相続による売却、自動車の名義変更、遺産の換価・分配等を弊所の司法書士・行政書士が代行します。
相続税の申告や遺産分割調停・審判については、司法書士が代理人として窓口となり、税理士・弁護士に依頼をしますので、お客様の手を煩わせません。
遺産分割協議についても、司法書士が専門家として中立の立場で情報提供や立会いをしますので、的確で安心です。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)のメリットやサービス内容、報酬等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
相続登記(不動産の相続による名義変更)
令和6年4月1日から、相続登記(不動産の相続による名義変更)は、法律上の義務となりました。
被相続人の死亡から3年以内に相続登記を申請する必要があります。(※令和6年3月31日以前に発生した相続については、令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません)
義務違反の場合には、過料の制裁が科せられるリスクもありますから要注意です。
相続登記の手続きについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
相続登記の義務化の制度、罰則、費用について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
相続放棄
相続放棄の手続きは、原則として、被相続人の死亡から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述をすることによって行います。
相続放棄をすると、その方は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、遺産のうちプラスの財産もマイナスの債務も全て相続しないこととなります。
3か月経過後でも、例外的に相続放棄ができるケースもあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
預貯金・株式の相続手続き(解約・売却)
金融機関の預金口座については、遺産分割協議でどの相続人が取得するかを決めた上で、解約の手続きをすることとなります。
株式については、取得した相続人の名義の口座を新設してそこに移管するか、売却して代金を相続人で分けるなどといった対応となります。
預貯金の相続について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
遺言書作成・検認手続き
相続が起きた際に、相続人間で揉めて欲しくない、お世話になった知人に遺産を譲りたい、前妻との子がいるので相続人間の話し合いが難しい、などといった場合には、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書を書くことにより、遺産の分割の方法を指定したり、遺産の取得割合を決めたり、未婚の子を認知したりすることができます。
遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書を作成した方がいいケースやメリット・デメリットについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
自筆証書遺言については、法務局での保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
検認の手続きについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
遺産分割調停・審判の申立て
相続人間で遺産分割を巡って紛争となってしまった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。
遺産分割調停では、話し合いによる合意を目指しますが、調停不成立となった場合は審判に移行します。
遺産分割調停の申立てについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
生前贈与
遺産を事前に贈与しておきたい、遺産分けの話し合いを回避したい、相続税を節税したいといった場合には、生前に財産を贈与しておく方法があります。
生前贈与について、不動産は贈与による所有権移転登記が必要となります。
また、生前贈与については、贈与税や不動産取得税がかかるリスクがあり、軽減・回避するために税理士と連携して対応します。
生前贈与について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の利用
相続で土地を取得したけれども、不必要な土地であり手放したいという場合、国に不動産を引き取って貰う制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属の利用には、草刈りや測量などの費用もかかりますが、長期間の固定資産税の負担と比較して検討するとメリットが見えてきます。
相続土地国庫帰属について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
以上、相続の各種手続きについてご案内しました。
相続の手続きについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。