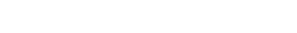今回は、司法書士の法律判断権と昭和52年の松山地方裁判所西条支部の裁判例である宗判決について、解説します。
このページの目次
司法書士の2つの相談業務
司法書士法には、司法書士が行う相談に関する根拠規定が2つあります。
1つ目は、司法書士の簡易裁判所での訴訟代理に対応した3条7号の相談規定です。
これは、弁護士法72条に言う「鑑定」を行うことができることを規定したものとなっています。
もう一つは、登記業務や裁判所提出書類作成に対応した3条5号の相談規定です。
登記に関して相談に応ずることができることに疑義はないのですが、法律事件に関して司法書士が裁判所提出書類を作成する際に行う相談の限界が問題となってきます。
その点について判事された裁判例として、古くは昭和52年の松山地裁西城支部の判決とその上訴審である高松高裁の判決があります。
書類作成相談の限界と高松高裁判決
高松高裁での判決は、司法書士の法律判断権を狭く解釈するもの(法律判断限定説)となっており、近年の学説からは批判の対象となっているところもあります。
というのも、簡裁代理権(140万以内の法律判断権)を持つ認定司法書士が、司法書士法第2条の誠実に業務を行う義務を果たそうとすると、書類作成業務(5号相談)においても、法律判断をすべきであると言えるからです。
さらには、令和元年の司法書士法改正により、司法書士法第1条に規定された使命規定は、司法書士を法律事務の専門家と規定しており、上記の高松高裁判決(法律判断限定説)と文言的に矛盾することからも、司法書士の法律判断権の解釈が変更されたとすべきではないでしょうか。(使命規定と法律判断権の関係について、詳しくはこちら)
いずれにせよ、昭和54年の高松高裁判決は、法改正によりその解釈が古くなっていると言わざるを得ませんが、一方で、その第一審の判決が司法書士の裁判書類作成業務の実態を的確に捉えたものでありました。
その判決を書いた裁判官の名前から宗判決と呼ばれ、司法書士の間では語り継がれてきた判決であると言われています。
内容としては、依頼人の依頼の趣旨に沿った司法書士の法律相談権を認める(目的的法的判断肯定説)もので、その後の司法書士の簡裁代理権の獲得にも大きく影響したとされています。
宗判決(松山地裁西条支部裁判例)の紹介
以下に判決理由を引用して掲載します。
第一、一弁護士法第七二条は、弁護士でない者は報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務を取り扱うことを業とすることはできない旨規定し、同法第七七条に罰則を設ける。右は、弁護士は基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、且つその職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上にはこのような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のためみだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、かかる行為を禁止するために設けられたものである。
二、而して、弁護士法第三条第一項は、弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とすると規定する。
即ち、弁護士は依頼者より法律事件について委任を受け、民事々件についていてば民事訴訟法第七九条により当事者の訴訟代理人となり、訴提起に始まり、準備書面の提出並びにこれらの陳述、証拠の申出等法廷における訴訟行為や証人尋問の実施等の法廷活動の他、同法第八一条所定の権限が与えられ、刑事々件についていえば、刑事訴訟法第三一条により被告人の弁護人となり証拠調の請求、異議の申立等被告人のなしうる訴訟行為を代つてする代理権、被告人との接見交通権、証拠の閲覧謄写等包括的に被告人の防禦権の行使に当るものであり、その他の非訟事件等についての申立権等、広く法律事件の紛議の解決を図るものである。
第二、一、他方、司法書士とは他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁又は法務局に提出する書類を作成することを業とする者をいう(司法書士法第一条)。
而して、司法書士は、その業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならない(同法第九条第二一条)。
二、尚、司法書士法施行規則第一六条は、司法書士は法令又は嘱託の趣旨に従わない書類を作成してはならない。司法書士は嘱託人の嘱託によらない書類を作成して報酬を受けてはならないと規定していたが、これは昭和四二年削除された。
第三、そこで、右弁護士業務と司法書士業務の関係が問題となる。
司法書士が作成する書類は、訴状、答弁書、告訴状、登記申請書類等、いずれをとつてみてもこれに記載される内容が法律事件に関係するものであるから、右書類作成については相当の法律的素養を有し法律知識がなければできないこと勿論である。国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。従つて、司法書士は書類作成業務にその職務があるのであるが、他人の嘱託があつた場合に、唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、その嘱託人の目的が奈辺にあるか、書類作成を依頼することが如何なる目的を達するためであるかを、嘱託人から聴取したところに従い、その真意を把握し窮極の趣旨に合致するように法律的判断を加えて、当該の法律事件を法律的に整理し完結した書類を作成するところにその業務の意義があるのであり、そこに法的知識の涵養と品位を向上させ、適正迅速な業務の執行ができるよう努力すべく、よつて以て国民の身近な相談役的法律家として成長してゆくことが期待されるところである(因みに、司法書士法第一条の「書類を代つて作成する」旨の規定が「書類を作成する」と昭和四二年法律第六六号によつて改正され、「代つて」が削除された)。けだし、法治国家においては、国民が啓蒙され一定の法律的知識ないし常識を有していることを建前としているが、現実は個別的具体的事件について国民一般の法律的知識は全く乏しいものといわなければならず、例えば裁判所提出の書類作成を依頼するについても単に表面的機械的に事情を聴取した上では何をどのように処理して貰いたいか全く不可解なことも多いのであり、これを聴取してその意を探り、訴を提起すべきか、併せて証拠の申出をすべきか、仮差押、仮処分等の保全の措置に出るべきか、執行異議で対処するかを的確に把握し、その真意に副う書類を作成するについて法律的判断がなされるべきは当然であるからであり、このような判断を怠つて、いたずらに趣旨曖昧不明の書類を作成して裁判所に提出させることをすれば、却つて裁判所の運営に支障を来すことは明らかであり、殊に弁護士の数が比較的少い僻地ではかようにして司法書士が一般大衆のために法律問題についての市井の法律家としての役割を荷なつているといえるのである。
かように見て来れば、弁護士と司法書士はともに国民の法律生活における利益を保護し、併せて司法秩序を適正に保護し、以て法律生活における分業関係に立つものといえる。沿革的にも、明治五年八月三日太政官無号達の司法職務定制に代言人、代書人の区別がみられ、明治六年七月一七日太政官布告第二四七号の訴合文例をみれば、代書人をして裁判所に持ち込まれる多様な形態の紛争を文例に従つてこれを整理し裁判所に導入する役目を果させ、且つこれに法的評価を加えさせているのであつて、代言人が訴訟上の口頭主義を担保すべき役割を果すべき存在として性格規定されていることに比べ、代書人は書面主義を担保する役割を与えられていたのである。
而して、本人の嘱託ないし委嘱、依頼は、かたや書類の作成であり、他は法律事務を行うことの依頼であり、その内容は異なるにせよ、司法書士、弁護士の両者ともにその法律上の性質は委任された事務の処理(民法第六四三条の委任)であることには変りがなく、弁護士に対しては包括的な法律事務を取扱うことの事務処理であり、司法書士に対しては個々の書類の作成という個別的な委任事務の処理が普通であろうが、依頼の趣旨によつては司法書士に対し或る程度包括的な書類作成事務の処理という包括的なものも考えられないではなく、従つて、右両者の区別を委任事務の個数によつて区別することは出来ないものといわなければならない。
もとより、前記司法書士の期待像からすれば、右書類作成の嘱託を受けるに当つて、依頼人から法律事件について法律相談を受ける場合もあるが、これが報酬を得るのではなく、又右書類作成嘱託の目的に反しない限り司法書士がその有する法律知識を活用して法律相談に応ずることは何ら差支えなく、弁護士法第七二条の規定は何も国民を法律的に無知蒙昧、即ちこれを法律的につんぼさじきに置こうとするものではない。
然しながら、右書類作成の域を超えて他人間の法律的紛争に立ち入つて書類作成に関係のないことまで法律事務を取扱うことは司法書士の業務に反し弁護士法第七二条に背反する場合も出てくるものといわなければならない。そこで、同条の解釈をする。
同条に所謂法律事件とは広く法律上の権利義務に関し争があり、疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する条件を指し、法律事務を取扱うとはこのような法律事件についてその紛議の解決を図ることを謂い、鑑定、代理、仲裁、和解等がその例として設けられている。鑑定とは法律上の専門的知識に基いて具体的な事案に関して判断を下し、代理とは本人に代わり本人の名において案件の処理にあたり、仲裁とは自らの判断による解決案を以て本人を納得させ紛議を解決し、和解とは自らの判断による説得を以て本人の紛議の解決を助成することを謂う。従つて、このことから法律事件紛議の解決は自らの意志決定によつて法律事件に参与し、右のような手段方法を以て自らの判断で事件の解決を図ろうとすることを謂うと解され、又それは報酬を得る目的を以て業とすることを必要とするが、現実にこれを得たと否とを問わない(そうすると、司法書士法第九条第二一条は訴訟を為す目的を以て他人の権利を信託的に譲渡を受けるとか、自己が代表者である会社に他人の権利を譲渡させるとか、司法書士が右弁護士法第七二条以外の態様によつて他人間の訴訟に関与することをいうと解される)。
このように、司法書士が右法律相談に応じることはできるにせよ、法律事件の解決はその委任を受けた弁護士の他は、専ら右事件の紛争主体である依頼人自身が自らの判断でこれを決すべきところであり、司法書士がたとい依頼人の委任を受けたところでこれをさしおいて自らの判断で事の処理に当ることはその職務に反し到底許されるところではない。
従つて、被告人の所為が弁護士法第七二条に違反するかどうかは、被告人のしたことが、右書類作成嘱託の窮極の趣旨を外れ、職制上与えられた権限の範囲を踰越し自らの意志決定により自己の判断を以て法律事件の紛議の解決を図ろうとしたものであるかどうかによつて判断すべきもの、即ち、右の権限踰越か否かが区別の本質的基準と考えられるのである。弁護士、司法書士ともその与えられた職務についてはこれを業とし報酬を得るものであり、又営利性も業務性も司法書士がその職制の範囲を踰越したことを前提としてその事項につきこれが営利を目的とし業とした時に問題となるものであるから、いずれも弁護士法第七二条の本質的基準となし難い。
以上になります。
司法書士法に、宗判決の言う法律判断権が明定されることを切に願っています。
(※なお、当事務所の司法書士の行う本人訴訟業務は、司法書士法に定められた業務範囲内において行うものです。)