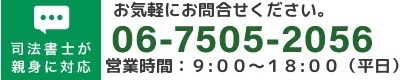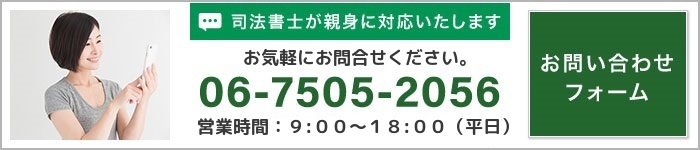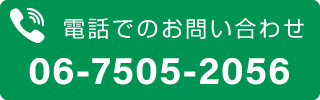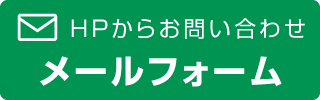事業承継やM&Aを進める上で、連絡が取れない株主(所在不明株主)の存在は大きな障害となり得ます。
そのような株主がいる場合でも会社が株式を整理できるよう、会社法には「所在不明株主の株式売却許可制度」が設けられています。
本稿では、この制度の趣旨・概要、具体的な手続きの流れ、制度の活用が求められる場面、そして中小企業の事業承継を支援する特例措置について解説します。
このページの目次
制度の趣旨と概要
所在不明株主とは、5年以上に渡り会社から送付する株主総会招集通知などが届かず、配当金も受け取っていない株主のことです。
長期間連絡がつかない株主がいると、株主総会の決議に必要な定足数・議決権数を満たせないなど会社運営に支障が生じる恐れがあります。この問題を解決するため会社法第197条では、所在不明株主が保有する株式について会社が裁判所の許可を得て強制的に売却(買い取り)できる制度を定めています。
株式の売却が許可されると、その所在不明株主は株主としての地位を失い、会社は株式を取得して必要な手続きを進めることが可能になります。
買い取った株式の代金は、法務局に供託することで株主への支払義務を果たします。
手続きの要件と流れ
この制度を利用して所在不明株主の株式を売却するには、法律で定められた要件を満たし手続きを取るがあります。
-
(要件) 対象となる株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合であり、かつ 5年間続けて配当を一度も受領していないことが必要です。
5年間配当が「無配」だった場合も配当未受領に含まれます。
また、対象株式が上場株式など市場価格のある場合を除き、競売以外の方法(任意売却)で処理することが相当である必要があります。これらの要件を満たす株式についてのみ、会社は裁判所に売却許可を申立てることができます。 -
(手順1) 公告・催告: 売却に先立ち、会社はその株式を売却する旨と「利害関係人は一定期間(※少なくとも3か月)内に異議を述べることができる」旨を官報などで公告し、該当株主の株主名簿の住所宛てに個別に催告(通知)します。
-
(手順2) 裁判所への申立て: 公告期間満了後、異議がなければ会社は管轄の裁判所(非訟事件を扱う地方裁判所等)に対し売却許可の申立てを行います。
申立人はその株式を発行した会社で、取締役が複数いる場合は取締役全員の同意が必要です。
申立ての際には、
①6年分の対象株式の株主に対する株主総会招集通知書、剰余金配当送金通知書及びそれらの返戻封筒
②株価算定書
③取締役会議事録(又は取締役決定書)(会社法197条3項)
④官報(会社法198条)
⑤対象会社の履歴事項証明書
⑥取締役全員の同意書(取締役が複数の場合)
⑦催告書及びそれを発出したことが判る資料(会社法198条)
⑧買取書
を添付して提出します。 -
(手順3) 裁判所の許可決定: 裁判所が要件充足と売却の相当性を認めると、売却許可の決定が出されます。許可決定がおりれば、会社は当該株式を予定どおり売却することができます(一般的には会社自身が買い取るケースが多くなります)。
-
(手順4) 代金の供託: 最後に、買い取った株式の売却代金を法務局に供託します。
以上が売却許可制度の基本的な流れです。
なお、手続き全体には公告期間の3か月に加え、申立て準備や裁判所での審理期間も必要になるため、一定の時間を要します。
また、株主が行方不明でも株主名簿上は存在しているため、5年に満たない段階で勝手に株主を除外することはできません。
したがって、日頃から株主総会通招集知を送付し記録を残す必要があります。所在不明株主がいる場合は早めに弊所の司法書士等の専門家へ相談することが重要です。
制度の活用が必要となる場面
所在不明株主の株式売却許可制度は、主に非上場企業において次のような場面で活用が検討されます。
-
事業承継(経営者の交代): オーナー経営者が引退や世代交代を予定している際に、一部の株式を持つ株主と長期間連絡が取れないケースです。
後継者への株式集約ができないと事業承継が円滑に進みませんが、本制度を使って所在不明株主の株式を整理すれば、後継者に株式を集中させ円滑な承継が実現できます。 -
M&Aや企業再編: 他社とのM&Aや、グループ内での合併・株式移転などを行う際にも、本制度の出番があります。
株主総会の特別決議が必要なスキームの場合、所在不明株主が多数いると必要な議決権数を満たせず承認決議ができなくなる恐れがあります。
その結果、せっかく進めていたM&Aを断念せざるを得なくなったり、スキームの変更を迫られるケースもあります。
なお、特別支配株主による株式等売渡請求や株式併合などのスクイーズアウトができる場合は、そちらを検討した方がスムースに進む場合があります。(詳しくはこちら)
以上のように、所在不明株主の問題は経営の将来的な障害になり得ます。
特に中小企業では株主の人数がそもそも少ないため、一人でも所在不明になると影響が大きいものです。早めに対応できればベストですが、5年という要件がネックになるケースもあります。
次章では、その5年要件を特例によって短縮できる制度について説明します。
経営承継円滑化法による特例(公告期間の短縮措置)
中小企業の事業承継を円滑化するため、2021年の法改正により所在不明株主の株式売却許可制度には特例措置が設けられました。
これは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)に基づく制度で、一定の条件を満たした中小企業については先述の5年という(行方不明の)期間要件を1年に大幅短縮できるものです。
特例の概要: 非上場の中小企業で、代表者の高齢化や健康不安により経営の継続が難しくなっており、なおかつ一部株主の所在不明によって後継者への円滑な事業引継ぎが阻害されている場合に、都道府県知事(経済産業大臣から権限委任)に申請して認定を受けることができます。
この認定を受けた企業には特例が適用され、所在不明株主に対する通知不達・配当未受領の要件が「1年以上」に短縮されます。
ただし、この特例を利用するには追加の手続的保障が課されています。具体的には、通常の公告・催告手続に先立ち、特例を利用する旨を明示した公告と催告を別途行う必要があります。
認定の要件は、以下のとおりです。
・経営困難要件:申請者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること
例:代表者が60歳以上、代表者の健康状態悪化、幹部の病気や事故etc
・円滑承継困難要件:一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること
①株式譲渡でのM&Aが決まっている場合は、所在不明株主の議決権割合が1/10超かつ(1-要求される割合)超
②事業譲渡や会社分割、新株発行等の株主総会特別決議が必要な場合は、所在不明株主の議決権割合が1/3超
③事業承継の相手が決まっていない場合は、所在不明株主の議決権割合が1/3超(例外あり)
解説は以上となります。所在不明株主の株式売却許可制度のご利用については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。