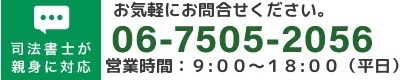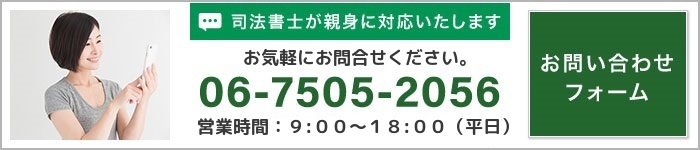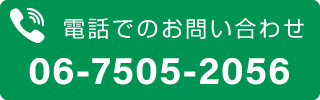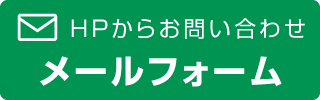物損事故での損害賠償請求にも法律事務の専門家である司法書士が対応致します。
自動車やバイクを運転していて、不幸にも交通事故に遭ってしまうことがあります。被害者に怪我がなければ人身事故とならず、物損事故として扱われることとなります。
当方が被害者である場合の物損事故であっても、加害者又はその保険会社と交渉し、修理費や代車費用などの損害賠償金を支払ってもらう必要があります。通常は、依頼者様側の保険会社が交渉にあたってくれるものと思います。
しかし、以下のようなケースにおいては、ご本人様や保険会社での対応が難しくなりますので、当事務所にご相談下さい。(以下、司法書士が代理人として交渉や裁判をするのは、請求額が140万円までの事件となります。)
このページの目次
追突事故や赤信号無視など、明らかに過失割合が10:0であるような事故の場合
被害者側に過失がない場合は、被害者側の保険会社が交渉できませんから、加害者側との交渉を自らする必要が生じてきます。
そのような場合には、当事務所の司法書士にご依頼頂ければ、代わりに交渉することができます。また、相手方の提示する金額に納得いかない場合は、訴訟の提起も可能です。
出会い頭の事故などで、保険会社の提示してくる過失割合に納得がいかない。
保険会社の交渉の中で提示された過失割合が必ずしも正しいものとは限りません。司法書士などの法律家が交渉することにより、不利な認定を避けられ有利な割合となるケースもあります。
また、過失割合については、裁判基準では修正要素が考慮されます。
例えば、交差点での出合い頭の事故において、見通しの良い交差点であることが判明すれば、左側の自動車の過失割合が10%下がることとなるといった具合です。
司法書士が任意での交渉をする際は、上記の修正要素が考慮された裁判基準に基づいてご依頼者様が不利にならないように交渉します。また、どうしても合意に至らない場合は、訴訟を提起することも考えられます。
加害者側の保険会社の提示してくる損害賠償金が安いため、納得がいかない。
車両の修理費が事故時の時価を上回る場合、全損となり賠償額は事故時の時価となります。この場合に、相手方の保険会社から提示してくる車両の評価額が安いことがあります。
また、評価損といって、修理歴のある自動車は価格が低下することから賠償が認められるケースがあります。これについて、保険会社が認めていない場合は、交渉の余地があります。
相手方が任意保険に入っていない。
加害者であるにもかかわらず、損害賠償に応じる様子がない場合は、司法書士などの専門家による交渉や訴訟により、損害賠償を実現します。
弁護士費用特約があれば、費用の面の心配はありません。
近年の任意保険には、弁護士費用特約が付いていることがかなり多くなっています。
弁護士費用特約とは、加害者に対して損害賠償したり、被害者から損害賠償請求を受けた場合の法律相談費用や弁護士・司法書士の報酬について、保険から支払われるものです。
弁護士費用特約で支払われる保険金の限度は、通常、300万円となっているようです。また、弁護士費用特約は、通常、保険加入者だけでなく、配偶者、同居の親族や別居の未婚の子にも適用がありますので、ご自身が加入していなくても家族の保険が使えないか確認する方がよいでしょう。
弁護士費用特約があれば、費用の心配はありませんし、費用倒れになることを防げますので、請求額が少額であってもお気軽に当事務所にご相談下さい。
加害者が任意保険に入っていない場合の損害賠償請求の手順と方法
1. 初動で“証拠”を押さえる
-
警察を呼ぶ→交通事故証明書(後日、裁判で要)
-
現場・車両・相手車の撮影(衝撃位置・停止位置・ブレーキ痕など)
-
ドライブレコーダーのバックアップ(上書き注意)
-
修理見積→修理請求書・領収書(物損は加害者の自賠責保険の対象外。かかった費用の証拠の確保が必要です)
2. 物損で請求できる主な項目
-
修理費(全損なら時価+買替諸費用)
-
レッカー費・保管料
-
代車料
- 休車損害:タクシーなどの営業用車両で、代車が使用できない場合に、修理・買替相当期間中の営業利益の賠償が請求できます。
-
評価損(事故歴による価値下落):賠償が取れない可能性もあります。年式・損傷部位・修理方法で成否が分かれます。
3. 任意交渉——内容証明で“期限”を切る
加害者が任意保険に入っていない以上、相手本人と交渉(又は訴訟)して、賠償金を支払わせる必要があります。
任意に賠償金を支払わない加害者に対しては、内容証明郵便を送付します。①請求額内訳、②法的根拠、③支払期限、④振込先、⑤遅延損害金(法定利率)などを記載しておきます。
分割での支払い希望があれば示談書を作成し、期限の利益喪失条項や連帯保証、強制執行認諾(公正証書の場合)など“効く条項”を入れます。
賠償金の支払いに、応じない/黙殺なら提訴へ。
4.簡易裁判所での通常訴訟と少額訴訟、どちらにする?
-
簡易裁判所では、原則として、訴額が140万円以下の事件を扱います。
-
少額訴訟…60万円以下の金銭請求なら簡裁で利用可。原則1回期日で判決が出る迅速手続です。ただし相手が望めば通常訴訟へ切替られてしまいます。また、控訴ができません。
実務上は、急ぎの事情がないのであれば、少額訴訟ではなく、通常訴訟で対応する方がよいでしょう。
5. どこの裁判所に出す?——管轄の押さえ方
原則は被告(加害者)の住所地の裁判所。ただし義務履行地(金銭債務は債権者=被害者の住所地)や不法行為地(事故地)でも提訴できます。通いやすさ・回収戦略で選びましょう。
6.強制執行と財産情報の取り方
こちらの勝訴判決が出たにもかかわらず、加害者が賠償金を支払わない場合は、預金・給与・動産への強制執行(差押え)を検討。相手の財産が不明でも、以下の方法で判明する場合があります。
-
財産開示手続(裁判所に呼び出して名寄せさせる/虚偽・不出頭は刑事罰あり)
-
第三者からの情報取得手続(金融機関・市区町村・年金機構などから口座/給与先情報を入手)
7. 認定司法書士ができる支援
当事務所は140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理/少額訴訟の代理、内容証明作成に加えて、判決後の財産開示請求・強制執行(本人名義の書面作成)まで一気通貫で支援します。
訴額が140万円を超える場合でも、書面作成による本人訴訟支援が可能です。
物損事故による損害賠償請求は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。