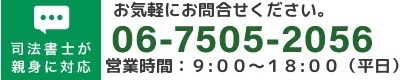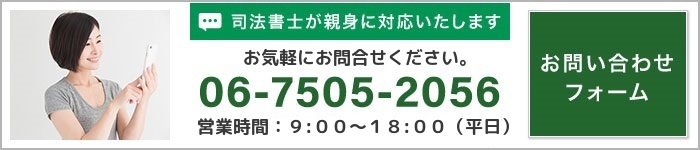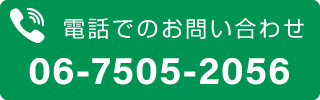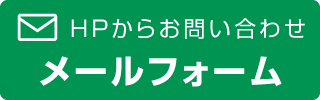今回は、業務委託契約を解除された場合、得られたはずの収入は損害賠償請求できるのか?逸失利益の計算方法や損益相殺について解説します。
このページの目次
想定事例
相談者X(業務受注者である個人事業主)
「発注元のA株式会社と●●●●について業務委託契約を結んでいて、契約書には“解除は30日前に通知する”と書いてありました。
ところがAから、何の予告もなく今日で契約終了と言われました。
この30日間で得られたはずの報酬は請求できますか? あと、空いた時間で別の事業所の仕事をして収入が入ったんですが、その分は差し引かれるんでしょうか?」
司法書士の回答
「結論から言うと、30日前予告条項に反して突然解除されたなら、30日分の報酬相当額(逸失利益)を損害として請求できる可能性が高いです。
ただし、解除期間中に同種の別の仕事で得た“代替収入”は、損害額から控除(損益相殺)されるのが原則です。
また、請求額が140万円以下なら認定司法書士が簡易裁判所で代理できますし、140万円超なら弁護士に引き継ぐか司法書士の本人訴訟支援で対応する形になります。」
業務委託の“突然解除”は違法になりうる
業務委託(準委任・請負)でも、契約書で「解除は30日前に通知する」などのルールを置いた場合、その合意に反する解除は債務不履行となり得ます。
つまり、解除自体がただちに無効になるかは別として、“約束された予告期間を奪ったこと”による損害賠償の対象になります。
逸失利益の計算式
突然の解除がなければ得られたはずの報酬は、一般に逸失利益(得べかりし利益)として評価されます。
典型的な計算式は次のとおりです。
逸失利益 =
(解除がなければ得られたはずの報酬)−(その仕事をしないことで浮いた費用(変動費))−(解除期間中の代替収入)
例えば
・本来の30日分の委託報酬
・交通費・消耗品費・材料費など“やらなかったことで不要になった支出”
・その30日間に他の事業で得た報酬
を上記の式に代入して計算していきます。
代替収入は損益相殺されるのか?
代替収入は、原則として差し引かれます。
理由はシンプルで、損害賠償は「解除がなければ得られたはずの利益」を回復させる制度であって、解除をきっかけに“二重取りで得をする”ところまでは認められないからです。
ポイントは、
・同種・同時期の収入か(解除期間と対応するか)
・解除がなければその仕事はできなかった関係か
となります。
たとえば「解除されても夜や休日に追加でできた仕事」など、本来の委託が続いていても両立できた収入なら、控除されない余地があります。
逆に、解除で空いた時間を埋めて得た収入なら控除対象になるのが基本です。
“浮いた費用”の控除も忘れずに
報酬が丸ごと損害になるわけではありません。業務をしないことで
・ 交通費
・備品・材料
・外注費
などが不要になったなら、その分は損害から引かれます。
専門的に言いますと、売上から変動費を控除した「限界利益」の請求が損害賠償の基本となるということです。
司法書士ができる対応範囲
認定司法書士は、140万円以下の請求について簡易裁判所の訴訟代理が可能です。
140万円を超える場合でも、本人訴訟支援として裁判所提出書類の作成・サポートが可能です。(司法書士法・弁護士法に定められた範囲内で行います)
まとめ
業務委託契約で「30日前予告」などの解除ルールがあるのに無視された場合、その期間に得られたはずの報酬は逸失利益として損害賠償請求できる可能性が高いです。
ただし、浮いた費用や解除期間中の代替収入は控除(損益相殺)されるのが原則となります。
業務委託契約等の解除に伴う損害賠償については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。