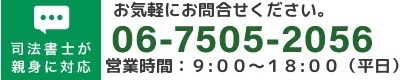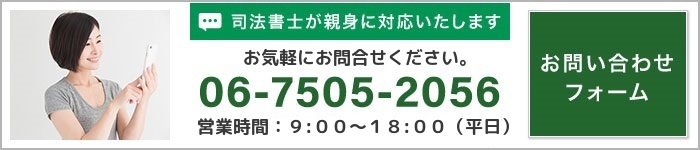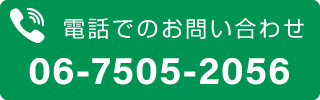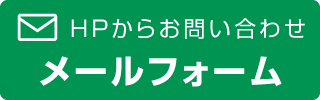今回は、建物明渡しの際に賃借人に支払う立退料の計算と、公共事業による用地交渉時の補償金としての借家人補償や不動産鑑定基準との違いについて解説します。
国土交通省四国地方整備局で用地買収(立ち退き交渉)に10年近く携わった弊所司法書士による解説となります。
このページの目次
建物明渡しにおける立退料とは
建物明渡請求の種類
不動産の所有者(大家さん)が、賃借人に対して建物明渡しを請求する場面は以下の種類に分けられます。
① 賃借人に契約違反がある場合(賃料滞納、建物の目的外使用、M&Aに関するCOC条項違反等)
② 賃貸借契約の更新を拒絶する場合
③ 貸主が、賃貸借契約の解約を申し入れる場合
①については、債務不履行による契約解除となりますので、立退料を考慮することは必要ありません。
②について、建物の賃貸借契約は、定期賃貸借契約や一時使用である場合等を除き、期間満了時に自動的に更新され、期間の定めのない賃貸借契約となります(借地借家法26条)
更新を拒絶したい場合は、期間満了の1年前から6か月まえまでに、賃借人に対して、更新をしない旨の通知をしておく必要があります。(借地借家法26条)
そして、更新拒絶には、上記通知のほか、正当事由が必要となります(詳細は後述します。借地借家法28条)
③について、貸主からの賃貸借契約の解約申入れをすると6か月を経過することによって契約が終了しますが(借地借家法27条)、ただし、これには、正当事由が必要となります。(詳細は後述します。借地借家法28条)
解約・更新拒絶の正当事由とは
借地借家法28条によると、
・建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
・建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況
・並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出(=これが、いわゆる立退料)
を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃貸借契約の解約や更新拒絶をすることができません。
借地借家法における立退料の意義
貸主側に、対象建物を必要とする事情が非常に強く存在し、かつ、賃借人側には対象建物を必要とする事情がほぼないような場合には、貸主に正当事由ありとして、立退料を支払うことなく、賃貸借契約の解約や更新拒絶をすることができる場合があります。
一方で、貸主の対象建物を必要とする事情はあるが、賃借人側にも対象建物を必要とする事情があるような場合には、貸主の正当事由が弱い状態となり、賃貸借契約の解約や更新拒絶が難しい状況となります。
そういった場合に支払われる立退料は、貸主側の正当事由を補完する役割を果たします。(最高裁昭和27年3月18日判決)
立退料の支払いにより、正当事由が満たされて、賃貸借契約の解約や更新拒絶が認めらることとなる場合があります。
立退料の計算方法
立退料の内訳
借地借家法における立退料というのは、上述のとおり、正当事由を補完する性質のものであるため、事例に応じて千差万別となり、一定の計算式を用いることで機械的に計算できるものではありません。
似たような事情・状況の裁判例を当たり、目途を付ける方法が一般的かと思います。
一般的には、立退料は次の3つの内訳を持っていると言われています。
①賃借人の移転費用の補償(引っ越し代金、移転先取得の手数料・費用、家賃差補償等)
②賃借人が事実上失う利益の補償(営業補償)
③消滅する借家権に対する補償
どんなケースにどの立退料を支払うべきか
どのようなケースの場合に、上記①~③のどの補償(立退料)を支払うのかについて、強いて分類するとすれば、以下のようになります(「どんな場合にいくら払う?!立退料の決め方」横山正夫他著P55、56)
1.立ち退かせるにつき理由が万全の場合・・・①の立退料
2.立ち退かせるにつき理由はあるが万全とは言えず、また賃借人側にも対象不動産の使用の必要性がある場合
・・・①と②(事例によっては③も)の立退料
3.立ち退かせるにつき理由がない場合・・・①と②と③の立退料
損失補償基準や不動産鑑定基準では
上述のとおり、(民事における)立退料は機械的に計算できるものではありませんが、公共事業の場合の損失補償基準や不動産鑑定基準が計算の参考にはなります。
損失補償基準による借家人に対する補償金
公共事業による用地買収(立ち退き等)に際して支払われる補償金は、国の場合は閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(地公体の場合は用対連基準)によって計算されます。
その中には、買収対象となる起業地に存する建物に賃借人がいる場合に支払われる借家人補償や動産移転料、移転雑費というものがあり、計算方法が規定されています。
公共事業での補償金は、民間の賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れとは異なり、起業者(国、地公体等)が公共事業のために、地権者(借家人)に対して任意の立ち退きを求める際に生じる損失を補償する性質のものです。
従って、公共事業のための立ち退きは、正当事由の補完ではなく、(任意に)立ち退きをする借家人に生じる損失に対する正当な補償がなされるかどうかという観点で計算されます。
借家人に対する補償の内訳は、主に借家人補償と動産移転料、移転雑費という項目になります。
移転雑費
・移転先又は代替地等の選定に要する費用
・法令上の手続に要する費用
・転居通知費
・移転旅費
・その他の雑費
・就業できないことにより通常生ずる損失の補償
動産移転料
1 屋内動産の移転料については、次により算定する。
「屋内動産」とは、居住用家財、店頭商品、事務用什器、その他の動産で普通引越荷物として取扱うことが適当なものをいう。
屋内動産の移転費は、建物の占有面積及びその収容状況を調査し、地域における標準的な一般貨物自動車の運賃により算定する。
2 一般動産の移転料については、次により算定する。
「一般動産」とは、木材、薪炭、石炭、砂利、庭石、鉄鋼、据付けをしていない機械器具又は金庫その他の動産で、容積及び重量で台数積算を行うのが適当なものをいう。
一般動産の移転費は、品目、形状、寸法、容量、重量その他台数算出上必要な事項を調査し、前項の例により算出する。
3 前2項の場合において、取扱いの困難な動産については、その実情に応じて梱包、積上げ及び積卸し人夫賃、易損品割増料、その他必要と認める特殊経費を加算することができる。
→ 要は、荷物の引越し費用の補償金となります。
借家人補償
賃貸借契約において借家人に返還されないことと約定されている一時金:標準家賃(月額)×補償月数
賃貸借契約において借家人に返還されることと約定されている一時金
:(標準家賃(月額)×補償月数-従前貸主からの返還見込額)×( (1+r)n-1)/(1+r)n
※rは年利率、nは賃借期間で通常10年(※上記式は、一時金の運用益を現在価値に割り戻しています)
家賃差補償:(標準家賃(月額)-現在家賃(月額))×12×補償年数
※補償年数:家賃差が3倍超は4年、2倍超3倍以下は3年、2倍以下は2年(国土交通省損失補償取扱要領)
不動産鑑定基準における借家権価額の算出
不動産鑑定基準 各論第1章第3節 Ⅲ借家権
(不随意の立ち退きの場合)・・・当該建物及びその敷地と同程度の代替建物等の賃借の際に必要とされる新規の実際支払賃料と現在の実際支払賃料との差額の一定期間に相当する額に賃料の前払的性格を有する一時金の額等を加えた額並びに自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し、所要の調整を行って得た価格を関連づけて決定するものとする。
→差額賃料法と控除法を関連付けて決定する、ということになります。
また、割合法というものがあり、簡便で参考として使われるので紹介しておきます。
(建物価格×借家権割合)+(土地価格×借地権割合×借家権割合)=割合価格
※借家権割合は税務上は30%ですので、30%がよく使われます。
以上、建物明渡しの際に賃借人に支払う立退料の計算と、公共事業による用地交渉時の補償金としての借家人補償や不動産鑑定基準との違いについて解説しました。
固定資産税評価額が280万以下(評価額が一棟の場合は部屋の面積按分で算出)となる建物の明渡し交渉や訴訟、それ以上の金額の場合の本人訴訟支援は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。