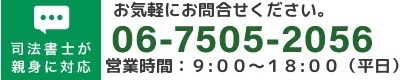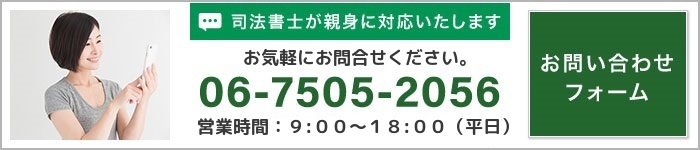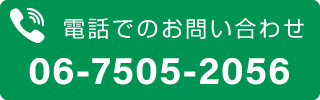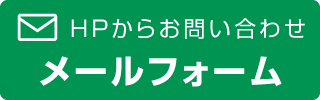今回は、不当解雇(解雇無効)を本人訴訟で争う方法とポイントを、事例やQ&Aを交えつつ解説します。
このページの目次
不当解雇とは
不当解雇とは、合理的理由や相当性のない解雇、法律で解雇が禁止されている場合における解雇、就業規則に違反した解雇等のことを言います。
不当解雇の中でも多いのは、労働契約法16条違反の解雇で「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効」と定められており、裁判例でも同様に「解雇権の濫用」として無効と判断されています。
この上記労働契約法16条は、普通解雇においても懲戒解雇においても適用があります。つまり、会社が安易に解雇できるわけではなく、労働者の解雇には厳しい要件が求められています。
典型的な不当解雇の事例
-
能力不足:業務が苦手、成績不振、などを理由に解雇された場合。
裁判例では「平均的な水準に達していないだけでは不十分。著しく労働能率が低く、向上の見込みがない場合でなければ解雇できない」とされています。
つまり、一般的に仕事が苦手というだけでなく、社内で極端な低さであり改善可能性がなければ正当とは認められません。試験の成績や人事評価も相対評価で変動するため、この基準は厳格です。 -
整理解雇(リストラ):会社の経営不振で人員削減する場合。
整理解雇が有効と認められるには「①事業の閉鎖・人員削減が経営上どうしても必要、②解雇者に他部署への配置換えなどの余地がない、③解雇対象者の選定が客観的・合理的な基準に基づく、④労働組合又は被解雇者と十分協議したこと」という要件がそろっていなければなりません。
たとえば、特定の工場を閉鎖する際に、会社内に受け入れ先があったのに解雇してしまった場合、整理解雇として認められない可能性があります。 -
即日の懲戒解雇:業務命令違反や私的な不適切行為などを理由に即日に懲戒解雇するケース。
社員が社内規律を乱しても、会社側が慎重にしかるべき手続きを経ていなければ、懲戒解雇は違法と評価される可能性があります。
通常、解雇は、注意や指導、弁明の機会の付与等、徐々に段階を踏むべきで、いきなり懲戒解雇すると違法とされることがあります。
実際の裁判例
過去の判例から、不当解雇と判断された例や有効とされた例を具体的に見てみましょう。
-
【セガ・エンタープライゼス事件 (東京地裁平成11年)】では、大学院卒の正社員Xが業績不振・協調性不足を理由に解雇されました。
裁判所は「・・・平均的な水準に達しているとはいえないし、Yの従業員の中で下位一〇パーセント未満の考課順位ではある。しかし、人事考課は、相対評価であって、絶対評価ではないことからすると、そのことから直ちに労働能率が著しく劣り、向上の見込みがないとまでいうことはできない。・・・体系的な教育、指導を実施することによって、その労働能率の向上を図る余地もあるというべき・・・」と判断し、解雇を無効としました。 -
【トラストシステム事件 (東京地裁平成19年)】では、派遣エンジニアXが派遣先で長時間私用メールや私的な人材あっせんをしたとして懲戒解雇されました。
しかし裁判所は「・・・服務規律違反、職務専念義務違反については、解雇を可能ならしめるほどに重大なものとまでいうことはできない。また、Yの指摘するXの能力不足についても、上記のとおり、解雇を理由づけるほどまでに能力を欠いているとは認め難い・・・」とし、この解雇を解雇権濫用として無効と判断しました。 -
【東洋酸素事件 (東京高裁昭和54年)】では、特定部門の閉鎖に伴う整理解雇について争われ、裁判所は解雇が「やむを得ない事業の都合」に該当するために「企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくこと」「他の部署への転換が不可能であること」「解雇対象の選定が客観的で合理性があること」の3要件を満たす必要があると述べ、解雇判断を支持しました。このように整理解雇は要件が厳格で、会社が恣意的に人員整理してはならないとされます。
これらの裁判例からも、単なる能力不足や行動ミスだけではすぐに解雇できないことがわかります。「客観的に合理的で社会的に相当」な理由がない場合、解雇は権利濫用として無効になるという点が判例でも一貫しています。
解雇無効とその効果
解雇が無効(不当解雇)と判断されると、法的には労働契約は継続しているとみなされます(地位確認)。
しかし実務上は、多くのケースで労使双方が和解で解決し、解雇後の賃金(バックペイ)や慰謝料など金銭的な支払いが行われます。
和解段階で「もし判決までいけばこのくらい払うだろう」という金額を基に支払いが決まります。
したがって、解雇が無効になると「未払い賃金の全額支払い」(解雇後も雇用契約が継続しているため)や「精神的苦痛に対する慰謝料」が認められる場合があります。
また、懲戒解雇の場合は退職金が支払われないことが多いので、解雇無効の和解で退職金相当額の支払いが認められることもあります。
労働審判と訴訟の違い
不当解雇の争いは、裁判所で行う「訴訟」だけでなく、より迅速な「労働審判」手続きも利用できます。
労働審判は3名(裁判官1名+労働審判員2名)の労働審判委員会が、最大3回の期日で解決を図る制度で、審理のスピードが特徴です。
訴訟の場合、期日に回数制限がなく1年以上かかることもありますが、労働審判は原則3回以内で審理を終え、数ヶ月程度で結論が出されることが期待できます。
また、労働審判は印紙代などの手続費用が通常訴訟の約半額で済むため、コスト面でも有利です。
さらに、審判員が企業実務に詳しいため、事実関係に即した柔軟な話し合いが進みやすい一方で、労働審判の決定に一方が異議を出すと訴訟に移行することになります。
異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同じ効力をもちます。
労働審判では、当事者の法律上の権利関係に固執することなく、また、申立事項に縛られず、当事者の事情や希望等を考慮して、柔軟な審判が出る点が大きな特徴です。
よくある質問と回答
-
Q:解雇が無効になったらどうなりますか?
A:法的には労働契約が継続するため、会社は雇用状態を元に戻す義務があります。しかし実際には、双方ともに再雇用を望まない場合が多く、未払い賃金(解雇から判決・和解までの期間分)や慰謝料が支払われる形で解決することが一般的です。
なお、会社が解雇通知後に退職届を要求してきても、無効を主張するために署名する必要はありません。 -
Q:不当解雇を争うには時効がありますか?
A:解雇が無効であると主張して従業員の地位を確認する手続き自体には時効がなく、解雇から1年後、5年後でも訴えることができます。
ただし解雇後の賃金請求は3年、慰謝料請求は3年というように、各請求権には別途時効があります。できるだけ早く行動することが大切です。 -
Q:司法書士に解雇無効の訴訟を依頼できますか?
A:可能ですが、弁護士のような代理権はありませんので、あくまで本人訴訟支援として裁判所提出書類の作成を行って、ご本人様の訴訟をサポートすることになります。
本人訴訟支援には金額の制限はありませんし、地裁以上の裁判所でも対応可能です。労働審判はもちろん、通常の民事訴訟での解雇無効についても支援可能です。
本人訴訟支援についいて、詳しくはこちらをご覧ください。(※本人訴訟支援は、司法書士法及び弁護士法に定められた範囲内で行います)
以上、不当解雇について本人訴訟で争う方法とポイントについて解説しました。
解雇無効の地位確認訴訟や賃金請求訴訟は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。