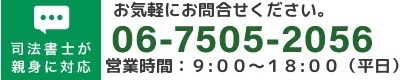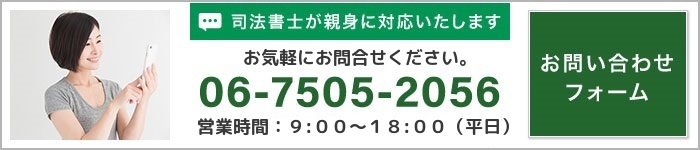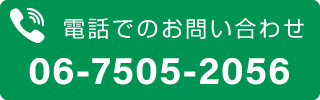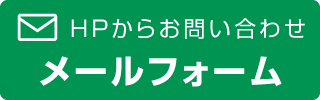今回は、他の相続人が相続登記に協力してくれない場合の訴訟対応と司法書士の本人訴訟支援・簡裁代理の活用について解説します。
このページの目次
遺産分割協議は成立したが登記に非協力的な場合は
不動産の相続登記では、相続人全員の遺産分割の話し合いがまとまり誰が不動産を引き継ぐか決まっていても、他の相続人が協力してくれないと登記の手続きが進まず困ってしまうケースがあります。
例えば、遺産分割協議書を作成する段階で非協力だったり、協議書はあるものの実印の印鑑証明書を提出してもらえなかったりすると、法務局への相続登記申請ができません。
そのままでは不動産の名義を書き換えられず、相続手続きが完了しないばかりか、第三者に権利を主張されるリスクや令和6年4月施行の相続登記義務化による過料の問題も生じかねません。
本記事では、そうした状況で取り得る法的・実務的な対応策について、不動産の現在の名義状態に応じて分けて解説します。
不動産の登記名義が被相続人のままである場合
まず、不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままになっているケースです。
通常、遺産分割協議が成立し特定の相続人が不動産を単独で相続することになった場合、その方が単独で相続登記の申請手続きを行えます。
しかし登記するためには、法務局に提出する書類として被相続人の除籍謄本や相続人全員の戸籍のほか、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書および各相続人の印鑑証明書が必要とされています。
そのため、協議書が用意できない場合や他の相続人が印鑑証明書を出してくれない場合には、書類が揃わず相続登記の申請が事実上できなくなってしまいます。
この状態を放置すると、不動産の名義がいつまでも被相続人のままで、不動産を売却したり有効活用したりできないだけでなく、相続人の一人が亡くなって相続関係がさらに複雑化するリスクも高まります。
遺産分割協議書が手元にない場合
遺産分割の話し合い自体はまとまっているものの、正式な遺産分割協議書が手元にないケースでは、二通りの状況が考えられます。
一つは他の相続人が協議書の作成自体に協力せず書面が作れない場合、もう一つは協議書は作成したものの原本を協力しない相続人が保持したままで入手できない場合です。
いずれにせよ、現時点で有効な協議書が手元になければ法務局への相続登記申請に必要な「相続を証する書面」が欠けており、このままでは単独相続人として登記申請を行うことができません。
対応策: 一つの方法は、協力しない相続人を被告として「不動産の所有権確認訴訟」を提起することです。これは、裁判所に対して「その不動産は遺産分割協議により自分の所有になった」と確認を求める訴訟です。
勝訴して確定判決を得られれば、その判決書が不動産登記法上の登記原因証明情報の一部として認められるため、他の相続人の協力がなくても単独で相続登記を申請することができます。
また、遺産分割協議の成立そのものを巡って争いがある場合(口頭では合意したが後になって内容を否認されている等)には、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てる方法も考えられます。
調停手続では調停委員を交えた話し合いで合意形成を試み、合意できれば調停調書が作成され、それがそのまま登記申請に使える書面となります。
もし、調停でも不調に終わった場合は審判手続(裁判官による分割の決定)に移行し、最終的には裁判所の審判によって遺産分割の内容が確定します。
調停調書や審判書は、協議書がない場合の公的な証明書となるため、それを添付して相続登記を申請することで他の相続人の同意がなくても登記が可能です。調停・審判の手続きには時間と手間がかかりますが、協議書を作成できない状況では有力な解決策となります。
遺産分割協議書はあるが印鑑証明がない場合
次に問題となるのは、協議書自体は相続人全員の実印で正式に作成されているものの、一部の相続人が印鑑証明書の提出に応じないケースです。
協議書に実印が押されていても、それが本人の押印であることを証明するための印鑑証明書がなければ、法務局は協議書を登記原因証明情報として受け付けてくれません。その結果、書類一式が揃わず相続登記の申請が止まってしまう状態になります。
対応策: この場合も、裁判所の力を借りて問題を解決する方法があります。もし協議書の原本が手元にあるなら、非協力的な相続人を被告として「遺産分割協議書の真否確認の訴え」を提起することが考えられます。
これは、その協議書が真正に成立した有効なものであることを裁判所に確認してもらう手続です。裁判で協議書の有効性が認められ、勝訴判決が確定すれば、その判決書をもって法務局に登記申請することが可能になります。判決により協議書の信用性が担保されるため、印鑑証明書がなくとも登記官が登記を受理できるようになるわけです。
ここで注意したいのは、「相手に協力するよう判決で命じてもらえば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、不動産の相続登記において他の相続人は本来申請人ではないため、相手方に登記手続きをせよとの判決を得ても登記申請自体は進まないという点です。
実務上も、遺産分割協議書の押印と印鑑証明書の提供はあくまで登記申請に必要な協力行為ですが、相続登記の申請そのものは先述のとおり単独でできる建前です。そのため、相手に「登記手続をせよ」という判決ではなく、協議書の有効性や自らの権利(所有権)の確認を得る判決を活用して単独申請する方法を取ることとなります。
以上のように、協議書さえあれば裁判で印鑑証明書欠如の問題はクリアできますが、裁判には時間や費用がかかります。協議書作成時になるべく早く印鑑証明書も取得しておくことが望ましいのは言うまでもありません。
不動産の登記名義が法定相続人の共有に移転済みの場合
次に、不動産について既に相続人全員の共有名義に変更されているケースです。
これは、遺産分割協議がまとまる前であっても相続人の一人が保存行為として法定相続分どおりの相続登記を申請したような場合に見られます。
共有名義への相続登記は、他の相続人の協力を得ずとも戸籍等の必要書類だけで申請できる点で有用ですが、最終的な遺産分割協議の結果として一人の名義にするには改めて持分の移転手続きが必要になります。
では、遺産分割協議が成立して「不動産は特定の相続人Aが全部取得する」という内容が決まったものの、他の共有相続人が協力してくれない場合はどうすれば良いでしょうか。
共有名義になっている不動産で遺産分割の内容を反映させるには、「遺産分割」を原因とする持分移転登記という形で手続きを行います。
具体的には、遺産分割により持分を得る側(取得持分が法定相続分より増える相続人)を「登記権利者」、持分を失う側(取得持分が減少またはゼロになる相続人)を「登記義務者」として、原因日付に遺産分割協議成立日を記載し、共同申請で登記を申請します。
これは通常の不動産売買などの移転登記と同様に共同申請の形式を取るため、本来であれば権利を得る人と失う人の双方が協力して申請書に署名押印し、必要書類を提出する必要があります。
問題点: 他の相続人がこの共同申請に協力しないと、持分移転の登記手続きが進みません。
例えば、相続人B・Cが登記義務者(持分を渡す側)であるのに、Cが「登記はしない」と言って書類への署名押印や印鑑証明書の提供を拒んでいるような場合です。
協議自体は成立しているのに共有状態が解消できず、Aとしては不動産を単独処分できないなど不便が残ることになります。加えて、この状態を放置すると、共有者である他の相続人が自分の持分を第三者に譲渡したり、持分に抵当権を設定するといった行為を行う可能性もゼロではありません。
せっかくAが不動産を取得する合意になっていたのに、共有持分の一部に他人の権利が入り込んでしまえば、問題がさらに複雑化してしまいます。
対応策: こうした場合、最も確実な方法は裁判を通じて持分移転登記を実現することです。
具体的には、非協力の相続人(登記義務者)を被告として「遺産分割を原因とする持分移転登記手続請求訴訟」を提起し、判決で相手方に登記手続をするよう命じてもらいます。
この訴訟は「被告は、原告に対し、本件不動産について、令和〇年〇月〇日遺産分割を原因とする持分移転登記手続をせよ」という判決を求めるものです。勝訴して確定判決を得れば、その判決書があれば相手が協力しなくても登記申請が可能となります。
このように裁判手続きを経ることで、最終的には当初の遺産分割協議どおりに不動産を単独名義に戻すことが可能です。
司法書士による本人訴訟支援・簡裁代理での対応
上記の「不動産の所有権確認訴訟」や「遺産分割協議書の真否確認の訴え」、「遺産分割を原因とする持分移転登記手続請求訴訟」については、弁護士に依頼せず、司法書士による本人訴訟支援を受けて、訴訟を遂行する方法もあります。
法廷に立つ自信があるので自分で訴訟をしたい場合や、費用を抑えて訴訟をして相続登記を完了させたいというご希望がある場合は、弊所の司法書士にご相談ください。
(※本人訴訟支援は司法書士法、弁護士法の範囲内で行います。)
本人訴訟支援について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、紛争の額が140万円以下(土地は280万円以下)の場合は、司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますので、弁護士同様に代理での対応も可能です。詳しくは、弊所の司法書士にご相談ください。
登記請求訴訟を司法書士に依頼するメリットとしては、訴訟から登記申請までワンストップで対応できることや、提訴時に登記上の問題点を的確に把握して事前対策を打てるため、勝訴したけれど登記が入らないといった事態を防止できることがあります。
相続登記の義務化に注意
最後に、令和6年4月の法改正により相続登記の申請義務が創設された点にも触れておきます。
相続により不動産を取得した相続人は、自身が相続人であると知り、遺産である不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となりました。
過去に発生した古い相続についても3年の経過措置を経て義務の対象となりますので、まだ名義を書き換えていない不動産がある場合は注意が必要です。こうした制度面の変化も踏まえ、他の相続人が協力してくれない場合でも上記の対応策を活用しながら、できるだけ早期に相続登記を完了させることをおすすめします。
遺産分割協議は成立したが、他の相続人が登記に協力してくれない場合の訴訟や相続登記申請は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。